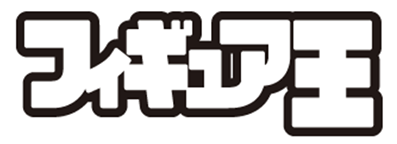インテリアスタイリストの窪川勝哉さんがクリエイティブディレクターの妻、飯嶌寿子さんと暮らす家は、築69年になるヴィンテージハウス。古い家や家具、クルマ、モノを愛してやまない窪川さんに家づくりの極意をうかがった。
写真/青木健格(WPP) 文/杉江あこ

窪川さんはインテリアスタイリスト&プロップスタイリストとして、テレビ番組や雑誌の企画、ウインドウディスプレイ、マンションのモデルルームなどのスタイリングで活躍。寿子さんは雑誌編集などを経た後、クリエイティブディレクターとして独立。

家を買うと決めた理由は?
高度経済成長期前の昭和30年代に建てられた鉄筋コンクリートの家は丈夫な造りが多いから。ヨーロッパの安宿のような外観も気に入ったポイント。

どうやって決めた?
不動産情報をチェックするのが趣味で、築年数の古い順に並び替えられるサイトで、いつも息抜きに古い家を眺めている。そこで思い出の家を見つけた。

住んでみてどう?
150%くらい大満足。来訪客も「実家みたいに居心地がいい」とたいてい言ってくれる。それくらい無の状態で居られる家。自分にとってはまさに聖域!

古い家を自分の手で快適に整えていきたい
窪川さんの自宅は、元々、学生時代に友人らと一緒に住んでいた賃貸住宅だった。そんな思い出深い家が売り出されていることを知り、32歳のときに購入したのである。海外生活をしていた期間には賃貸に出し、結婚した際には寿子さんが移り住むことで、18年間にわたってこの家の主人となってきた。
いったい、何に惚れてこの家を手に入れたのか? 「都心にこんなにも古い家が現存していることにロマンを感じた」と窪川さんは言う。一般的に新築や築浅の方が家の市場価格は高くなる傾向にあるが、窪川さんの考えは真逆。家に限らず、いつでも誰もが買える新品には魅力をあまり感じず、「レア感」や「掘り出し物」に惹かれるという。
しかし古い家であれば、当然、何かしらの不具合や不便はある。それを許容し、いかに楽しむ心をもてるかが住人の心得のようだ。「初めから快適過ぎるのは苦手。どうすれば暮らしやすい家になるのかを考えることでクリエイティブになれる」と能動的だ。ヴィンテージハウスをリノベすることの醍醐味は、海外生活で覚えたのだという。
一方、寿子さんは「普段、仕事で作り上げるスタイリング空間とはまったく違うテイストの家で、人肌を感じた」と初めて訪れたときの印象を振り返る。窪川さんにとっても、好きなものに囲まれた自宅はもっとも落ち着く場所のようだ。「家もインテリアも人も、すべてがヴィンテージだから緊張感がいっさいない。シミのひとつも気にならないくらいがちょうどいいんです」と話す。






Favorite corner