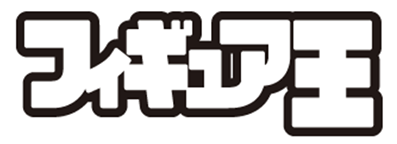ホンダのスポーツカー、S660の生産終了が発表されてしまった。スポーツカー不況と言われ始めた21世紀にホンダの心意気ここにあり、と男気をみせた1台で、世のクルマ好きはその存在自体に喜んだはず。
思い起こせば1990年代初頭、ベビーギャングと異名を持つリアル軽スポーツカーが大人気で、車名の頭文字をとってABCスポーツとかABC+Cとか専門誌で賑わっていた。もちろんAはマツダのAZ-1、Bはホンダのビート、Cはスズキのカプチーノ。そして+Cはダイハツのコペンだが年代に差があるため「+」がついていた。
マツダAZ−1。ミッドシップレイアウトでガルウィングドア採用が最大の特長。
当時量産車の中では一番低い車高と着座位置を誇った。また前後重量配分にも優れていた。腕のあるドライバーにはリアの剛性不足を感じさせたというが、このクルマが誕生したこと自体が奇跡的。乗ると囲まれ感が非常に強く、窓の開閉も限られており、駐車場のチケットを取る時などはドアをガバっと上にあげて取る必要がある。 筆者のようなマニアにはこの使い勝手の悪さこそスーパーカーっぽくっていいという少数派もいるはず。もしかするとM系体質なのかも。中古車市場では300万円オーバーのプライスをつけたクルマが多い。
そしてビート。1991年にミッドシップアミューズメントをキーワードにデビュー。

当時はバブリーな時代。クルマ好きの若人でさえハイソカーの人気が高かった。そんな時代背景ながらもあえて一切の虚飾を廃し、走りにベクトルを向けたモデルがビート。虚飾を廃したとはいえメカニズムは豪華だ。3連スロットルボディを採用。8100rpmまで回るエンジンはクルマの重量配分や重心位置低下のためとソフトトップの収納スペースを確保するためにわざと60度前傾させている。タイヤだって前後でインチが違う。フロントは13インチ、リアは14インチだ。回せば回すだけパワーの出るフィーリングはNAスポーツカーのそれで優れたハンドリングが魅力のひとつでもあった。
そしてライバルの中で唯一FRレイアウト(スズキ初)を持つのがカプチーノ。

スポーツカーの王道たるロングノーズショートデッキのデザイン。
ルーフには凝ったオープントップが備わる。このルーフは3つのパーツから成り立っており、フルオープン、タルガトップ、Tトップの3つを気分で味わえる。外したルーフのパーツはトランクに収納可能だ。もちろんリアスクリーンはガラス製。それでいて700kgという車両重量に組み合わされたパワフルなターボエンジンで遅い訳がない。1995年のマイナーチェンジではエンジンがオールアルミ製!!(軽自動車ですゾ)になり車重も690kgに。まさにライトウェイトスポーツカーだった。乗るとショートホイールベースにターボらしさを味わえるエンジンでじゃじゃ馬っぷりが魅力。
時代は流れ、上記のABCトリオも市場から姿を消してミニバンブームの中にダイハツから2002年にデビューしたのがコペン。

ABCトリオが気合いの入ったスポーツカーとするならばコペンはそのベクトルではないかもしれない。しかしスポーツカーといえばイエスだ。アクティブトップと呼ばれる贅沢な電動開閉式ルーフが特長。またこの部分の重量増をルーフやボンネット、トランクリッドをアルミ製にするなどこだわりのモデル。走るとFFの安定感をベースにリアのセッティングを専用とすることでクイックな味付けのハンドリング。人気車種となったコペンは2014年に2代目へとバトンタッチ。

そしてS660。

このクルマの企画自体は2010年の本田技術研究所の設立50周年を記念して社内で募集した「新商品企画提案」のグランプリに輝いたモノ。しかもその企画を提案したのは当時20代の椋本陵(むくもと りょう)氏。しかもホンダはその「若干」という言葉が似合いそうな若人を開発主査たるLPL(ラージプロジェクトリーダー)に抜擢したのだ。この柔軟さはさすがホンダ! と手を叩いたファンが大勢いたという。デビュー当時、椋本氏は「僕たちは完成した商品としてのクルマを提供することしかできないけど、一番届けたいのはスポーツカーのある楽しい暮らしなんです」と言っていたが、スポーツカーの存在こそクルマの楽しみ。
S660のレポートは後編へつづく。